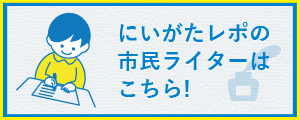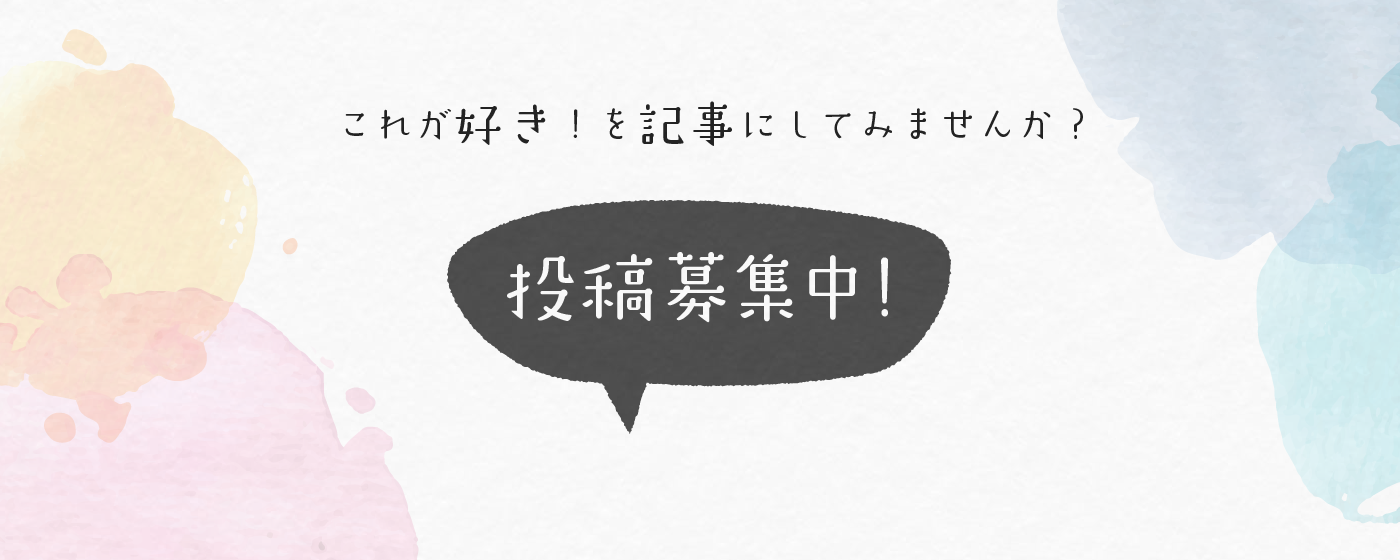日本酒の酒蔵数が88蔵(2020年4月現在)で日本一といわれる新潟県。古くから様々な地域で酒蔵独自の日本酒を造り続けてきました。そんな一大産地で、日本酒の質を追い求め、わざわざ山奥にある清水を汲みにいき、自社で酒米を作る酒蔵があります。
それは新潟県五泉市で150年以上に渡り、日本酒を造り続ける「近藤酒造株式会社(以下、近藤酒造)」。菅名岳の麓に広がる五泉市は、五つの泉が湧き出ると地名が語るように豊かな水に恵まれた地域です。
「この豊かな水と米を使って、本物の酒を造りたい」。
そう語るのは近藤酒造社長の近藤伸一さん。五泉の自然を活かした酒造りと蔵人の育成、そして仲間作りと次々に新たな取り組みに挑戦する近藤酒造の姿に迫ってきました。
▲代表取締役の近藤伸一さん
近藤酒造が創業したのは、江戸時代末期の慶応元(1865)年。大和屋和吉という人物が酒を醸したのが最初といわれています。3年後の慶応三(1868)年の酒家(酒造)を記録した『越後酒造史』には、五泉の吉沢に蔵元が6件もあったと残されており、酒造りが盛んな地域であったことが記載されています。
つまり、五泉は酒造りが盛んな町だったのです。その理由を近藤社長は「質の高い水と米、そして働き手があったから」といいます。
鉄分の少ない、酒造りに最適な水を求めて
現在、近藤酒造は毎年寒さがますます厳しくなる寒の入り(小寒)から9日目の寒九の日に、200名以上の参加者と共に菅名岳にある胴腹清水(どっぱらしみず)へ酒造りに必要な水を汲みに行っています。そして、その水を使って銘酒「菅名岳」を造っているのです。
今でこそ、多くの人が参加していますが、その始まりは平成4(1992)年に新潟県酒造組合が主催したマーケティング講座に参加したこと。
当時を振り返り、社長はこう語ってくれました。
「五泉で酒を造る意味を考えたときに、やはり水にこだわりたいと思いました。そんなときに当時の五泉市長(故 林十一郎氏)から教えてもらったのが、菅名岳の胴腹清水。早速、水を汲みに行くと、酒造りに良い柔らかな水でした。すると今度は、当時の五泉市下町郵便局の局長が寒の入りから9日目の“寒九の日”に汲むと良いという言い伝えがあると教えてくれました。そこで、平成4年に当時の蔵人や営業の従業員7人と、町の酒店の若手2人の計9人で汲みに行ったのが始まりです」。
この水を使って早速酒を仕込むと、スッキリとした味わいの日本酒が出来上がりました。酒造りには水の鉄分数値は低ければ低いほど良いといわれています。それは鉄分が高いと酒が劣化しやすくなるから。平場の井戸水の鉄分は0.01ppmなのに対し、清水は0.002ppmと、一桁違って鉄分量が少なくなりました。
こうした利点もあったことから、「寒九の水汲み」は毎年恒例の社内行事となりました。変わらず社員で水を汲みに行っていたところ、3年目に元京ヶ瀬村(現阿賀野市)消防署のレスキュー隊6人が飛び入りで参加。その様子を見ていた新潟日報の五泉支局長から「一般の方からも参加者を募ってみたら?」と助言をいただいたことで、翌年からは一般公募を行なうようになりました。
最初募集をかけて集まったのはなんと80人! しかも、その次の年には120人、240人…と次第に増えていき、2020年は平日の火曜日開催にも関わらず、232名もの人が集まりました。寒の入りから9日目と開催日が決まっているため、予定を調整することはできませんが、土日開催ともなると300〜400名もの参加者が集まるといいます。参加者にとっては酒造りに参加できるだけではありません。参加した特典として新酒をいの一番に手に入れることができるのです。この利点も人気の秘密。毎年リピート客が多く訪れるといいます。
こうして、近藤酒造の名物「寒九の水汲み」は一般からも認知されるようになっていったのです。
五泉で作った酒米で、酒を仕込む
水にこだわると近藤酒造はもう一つの原材料、米にもこだわろうと自社で米作りを始めることに。きっかけは平成14(2002)年に世界中で話題となった狂牛病問題でした。
当時、食品の安全を示すために栽培や飼育状態から加工・製造・流通などの全工程を明らかにする「トレーサビリティ」が話題となりました。近藤酒造としても同じように米の栽培履歴を開示できる体制を整えたいと、翌年から自社で米作りを始めることに。担い手のいない田んぼを借り、山の麓で酒米を育て始めました。
新潟県の農業普及センターの先生から育苗の仕方や田植えの方法、刈取りの仕方などを教えてもらいながら試行錯誤。平成15年〜17年は“五百万石”を、平成18年以降は酒米の最高峰の酒造特性を有する“越淡麗”を栽培しています。
寒九の水汲み、米作りを始めてから納得のいく酒に近づきつつあります。だから、次は仕込み。蔵人の育成を意識する段階へと変わっていったのです。
高品質の水と米を活かす、蔵人の育成
その昔、越後杜氏は酒を仕込む時期になると10名ほどの一団を各蔵に派遣し、寝泊りしながら酒を造り、終われば帰っていく。酒造り専門の出稼ぎのような形で酒造りを行なっていた時代がありました。
しかし、時代が変わるにつれ、だんだんと野積の蔵人が少なくなり、酒蔵は酒造りに困るようになっていきました。そこで立ち上がったのが、新潟県酒造組合。
昭和59(1984)年に酒造り技術を学ぶ「新潟清酒学校」を設立し、蔵人を育成していく仕組みをつくりました。酒蔵から推薦された人だけが入校を許され、正社員として酒蔵に勤めながら3年間月に1〜2回ほど授業に出席します。
▲現場での実習も(画像提供:新潟県酒造組合)
授業とはいえ、学校の建物があるわけではなく、新潟県醸造試験場や酒造組合を借りて実習講義を行ないます。講師は醸造試験場の研究員や酒蔵経営者、酒造技能者と第一線で活躍する人物ばかり。新潟県独自の教え方や方法、技術をみんなで共有しようと酒造組合が主導し、後継者育成を始めました。
▲近藤酒造でも蔵見学を行なった(画像提供:新潟県酒造組合)
近藤酒造も恩恵を受けているそうで、「うちの蔵人も4人中3人が清酒学校を卒業し、うち一人が杜氏を勤めています。蔵人の育成が課題となっている現在、これだけ育成の機会が整っているのはいち酒蔵としてもありがたいね」と社長も時折笑みをこぼしながら語ってくれました。
このような清酒学校が継続しているのは、世界で新潟県だけ。今や、88蔵にいる蔵人の半分以上が新潟清酒学校の卒業生だともいわれています。
こだわりの酒の良さを理解してくれる仲間をつくる
水、米、蔵人。良い酒を造る条件が整い、酒の品質は上がりました。しかし、酒蔵は日本酒を造ることだけが仕事ではありません。そのあとの届けるための酒販店との関係性づくりも酒蔵の大切な仕事。
「酒販店は価値を伝える接点です。蔵の言っていることをしっかりと理解して消費者に伝えてくれるところとお付き合いをしていきたい」。
▲近藤酒造の代表銘柄。左から「菅名岳 生九 特別純米酒」税込1,834円(720ml)、「菅名岳 生原酒」税込1,628円(720ml)、「菅名岳 大吟醸」税込3,960円(720ml)
そう社長が語るように、近藤酒造が造る日本酒の良さをしっかりと消費者に伝えてくれる酒販店のみに商品を卸しています。
そんな中で生まれたのが、契約を結ぶ酒販店を集めた「越後泉山会」。平成4年の寒九の水汲みを始めた際に組織を作り、現在の会員は県内で57名。近藤酒造の素材や人材育成に対する想いに共感してくれる人ばかりです。
「うちのような小さな蔵は良い酒を説明でき、蔵の想いを伝えてくれる酒販店に助けられています。これからも持ちつ持たれつの関係を続けていきたいです」。外から見ていても、寒九の水汲みや次に紹介する酒林づくりなど、酒販店は近藤酒造を慕っていることが目に見えて分かります。
▲越後泉山会のみなさんも参加する寒九の水汲み
そんな越後泉山会のメンバーと共に新酒ができる直前の毎年2月に酒林(さかばやし)づくりのイベントを開催しています。
酒林とは、別名杉玉とも呼ばれ、新酒ができた際に酒蔵の軒先に飾られるもの。飾られると杉は徐々に枯れていき、その変化は新酒の熟成具合を示すともいわれています。
近藤酒造と越後泉山会のメンバーは、そんな新酒の熟成を教えてくれる酒林を自分たちで作ろうと計画しました。まずは群馬に行き、作り方を習います。そして、酒蔵だけでなく、酒販店でも飾ろうと、一般の参加者も集い、誰でも参加できる仕組みを設けました。
「水汲みのように参加してこのくらい苦労しているのだなとわかれば伝えるし、酒林も作ればこれで訴えかけようとしているというのがわかる。越後泉山会はそれを理解し価値を一緒に作り上げていく集団でありたいと思っています」と、参加型のイベントを行う理由を教えてくれました。
杉からつくる酒林づくりの工程とは?
では、酒林はどのように作られているのでしょうか。酒林づくりの様子を見ていきましょう。
2020年は2月20日(木)に五泉市内の杉林の近くで行なわれました。
まずは横に張られた鉄棒に酒林を作るためのワイヤーをくくりつけます。そして、伐採された杉の葉と枝を少しずつ積んでいきます。
大きい枝も小さな枝もひとまず積んで、大まかな形を作っていきます。だいたいの大きさが出来上がったら、ワイヤーを強く止め、今度は丸くなるように剪定鋏で玉を作っていきます。
ここまでくると、見たことがある大きさになりますね。最後にはみ出た部分などを整え、ワイヤーを鉄棒から外したら完成です。
酒蔵や酒販店ではお店の前に飾り、お客さんに新酒の完成と、酒の熟成具合を伝えます。もちろん一般の方も参加OK。毎年開催しているようなので、気になる方は1月に入ったら、問い合わせてほしいとのこと。
本物の酒は人と人の縁を結ぶ。そのために酒を造り続ける
「海外進出に関しては、かなり慎重派だったんです」と近藤社長は話し始めます。
「日本酒がどのように伝わっていくかは非常に危惧していました。でも、数年前に新潟県酒造組合でシンガポールに行った際に駐在日本人に『こういう良い日本酒をもっと飲みたい。どんどん出してほしい』と言われたんです」

海外でも、良い酒を理解して楽しんでくれる人がいると知ってから社長の考えは変わっていきました。フランス料理に合うワイン型ボトルの日本酒「KAROKU」やアメリカ西海岸で広く流通する鹿肉にも合う日本酒「MIROKU」などを開発。伸び悩んだものの、伊勢丹三越のバイヤーに気に入ってもらい、日本国内のイタリア料理やフランス料理店で使われるようになりました。これからも闇雲に手を出すのではなく、愛着を持ってくださるファンを増やしたいと社長の目は未来を見据えます。
それは、社長が考えた日本酒の役割「日本酒とは、和材だ」との考えにも通じるもの。
「日本酒の役割とは何かと考えると、『話のタネになる話材』であり、『和みを与える和材』でもあるのではないかと思ったんです。日本酒には差しつ差されつという仕草があります。これは人と人を和する行為であり、お互いの理解を深めていくこと。良い酒は良い人を結ぶ。良い酒は人との関係性を取り持ってくれるんです」
本物の酒は人との縁を結ぶ。そのためにも本物の酒を造り続けることが使命だと語る近藤社長。水、米、人材、仲間作りにこだわり、次は日本酒の役割までも考えるようになりました。しかし、まだまだゴールは程遠い。近藤酒造の挑戦はこれからも続きます。
お問い合わせ
近藤酒造株式会社
○住所:五泉市吉沢2-3-50
○TEL:0250-43-3187
○HP:http://www.suganadake.com
※本記事の内容は取材・投稿時点のものであり、情報の正確性を保証するものではございません。最新情報につきましては直接取材先へご確認ください。